8月10日のサンマ漁解禁以降、水揚げ0が続いて、記録的な不漁が続いている。秋の味覚の王様「サンマ」が食卓から消えてしますのか?

どれだけ不漁なのでしょうか?
8月10日解禁の小型船(10トン以上20トン未満)、15日解禁の中型船(20トン以上100トン未満)の漁は、これまでの水揚げは皆無に近い。
1969年に次ぐ半世紀ぶりの不漁の2017年をしのぐ、危機的な状況であるといえるようだ。
解禁後に出漁した小型船は近海でしか操業できないため、「ほとんどが空振りで帰ってきた」であったり、日本の排他的経済水域まで足を延ばすことで漁獲できた船でさえも「わずかに水揚げしたのみ」だったという。
公海で操業する中型船でようやく水揚げがある程度で、日本近海に例年姿を現す「サンマ」が全く近寄っていないということになる。
サンマの不漁の原因はあるのでしょうか?
東京海洋大学 勝川俊雄准教授によると
「最近、日本周辺の水温が高いので、サンマが日本のそばを通らずに(日本の水域の)外側を通って卵を産みに(南に)行ってしまう年が増えています。 」
温暖化の影響による海水温の上昇で、サンマの回遊ルートが変化しているというのだ。
そして、もうひとつの理由は、海外でのサンマ漁が盛んになったこと。
中国や台湾のサンマ漁船は、一度に2500トンものサンマを凍らせて運ぶことが可能。近年、家庭で焼いたりバーガーに挟んだりと、サンマ料理などが大人気となっていることで、積極的にサンマ漁をしたい理由があるのだという。
そして、中国や台湾などは、サンマが日本に来る前の夏ごろに、自由に漁ができる公海でサンマを獲る。つまり、海外の船が、日本に回遊してくるサンマを先取りするかたちで漁をしているということになるのだ。
近年、台湾は漁獲量で1位だった日本を抜いた。中国も台頭している。

問題解決の道はあるのでしょうか?
日本は、国際会議「北太平洋漁業委員会年次会合」で、サンマの漁獲量に上限を設けることを提案し、資源量を回復させたいと狙ったが、日本案の日本の漁獲枠は24.2万トン、台湾は19万トン、ロシアは6.1万トン、中国は4.6万トンの漁獲高では、中国が納得せず、規制は成立しませんでした。

サンマに代わる救世主現れる?
サンマに代わって道東沖のマイワシの漁獲が好調だといいます。
ロシア200カイリ内で禁止されたサケ・マス流し網漁の代替で5月下旬から7月末まで行われたマイワシ漁の試験操業の漁獲量は過去最多を記録。道立総合研究機構釧路水試は「何らかの海洋環境の変化で、10~20年単位で主力魚種が変わる魚種交代が起きている可能性がある」と指摘している。
マイワシ漁は秋に最盛期を迎えるが、道東沖ではサンマやイカが主流だったが、現在は減少傾向。それに代わりマイワシが増えており、太平洋の資源は10年以降、増加が続いているという。

マイワシの食べ方と栄養素
〇いわしのなめろう
〇いわしの塩焼き








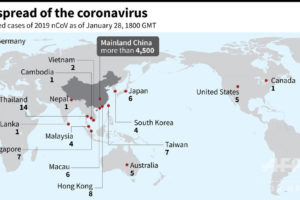




コメントを残す